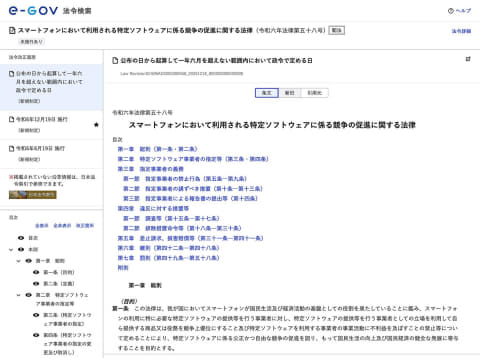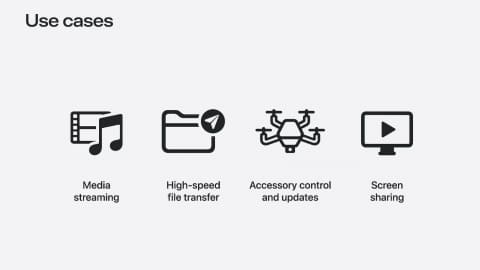西田宗千佳のイマトミライ
第298回
スマホ新法、アップルの示した「懸念」の意味とは
2025年6月23日 08:20
25年12月18日の全面施行を目指し、「スマホソフトウェア競争促進法」の準備が進められている。いわゆる「スマホ新法」だ。
6月13日にパブリックコメントの受付が終了したが、アップルもそこに詳細なコメントを提出したことを明らかにしている。
その内容を軸に複数の記事が公開され、本誌にも掲載されている。
ここでアップルがさまざまな懸念を表明するのはなぜだろうか。アップルの懸念はすべての面で正しいのだろうか。
今回は少し情報を整理し、「本質的にはどうあることが正しいのか」を考えてみよう。
スマホ新法の狙いは「公正競争」
スマホ新法の狙いはどこにあるのか?
法令は「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に掲載されているが、その第一条にこう書かれている。
この法律は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行なう事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行なう事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
重要なのは最後の「特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」というところだ。狙いは公正な競争であり、それに絡む規制も狙いは競争の維持だ。
アップルも、法のあり方自身を否定してはいない。法律ができた以上、それを遵守するという考えであるのは間違いない。
一方、法に示された内容の中でも、今後の運用の中で「課題が懸念される事項がある」と申し立てている。
「機能開放」はどうあるべきなのか
重視すべき点は主に2つある。
1つは、「機能へのアクセス開放の具体的条件が示されていない」ということ。
スマホ新法では、セキュリティの確保やスマホ利用者情報の保護を事由とする場合、OSの機能を解放する要求の対象外とする、と定めている。要は「セキュリティやプライバシー保護が弱くなる状況をもたらす場合には、公開の範囲外として良い」としている。
一方で、公開された機能がどう使われるのかについては、制約事項がない。
そのため、OSの機能を解放したとして、それが公正競争の維持ではなく、ライバル企業に有利で、プライバシーやセキュリティを脅かす懸念があるのでは……とアップルは主張している。
アップルは「すでにAPI経由で色々な機能を公開している」としており、用途や正当な理由の開示なく機能開示を求めることは、アップルと消費者にとって不利な状況を作るのでは……という話だ。
これは一理ある。
とはいえ、悪意ある使い方ばかりと考えるのも難しい。
以前他社にヒアリングした時の話では、「周辺機器の扱いについて、iOSとAndroidで差があるのが困る」という話でもあった。その多くは、接続の手順が多くなることや、公開されている機能の違いに起因するものだ。自由にデータアクセスして広告に使いたい……という話は出なかった。
ただ、全ての条件を飲む必要はないだろう。セキュリティを守るためにアップルが定めている手順をスキップできない……という話が多かったように思うが、それなら手順が違ってもしょうがない部分がある。
それ以外については、アップルが言うように理由を明示した上で許諾を考える仕組み、もしくは理由を明確に示せる部分でだけ公開するルールを定めてもいいのではないだろうか。
また、スマホ新法におけるiPhoneへの相互接続については、「国外の大手が主導して求めている」という意見もある。
5月には業界団体「オープンデジタルビジネスコンソーシアム」が設立された。スマホ新法での公正競争を目的とした団体ではあるが、同時に、設立メンバーはグーグル合同会社・クアルコムジャパン合同会社・Garmin International Inc.と、海外の大手どころが並んでいる。
日本にこの種のデバイスビジネスを行なう企業が減ったとはいえ、「大手がiPhoneという市場での競争力を高めようとしている」と言われてもしょうがない。
とはいえ、ライバルとしては「iPhoneユーザーにももっと売りたい」と考えるのは自然なこと。その上で、アップルのいう「セキュリティやプライバシーの懸念」と、ちゃんとバランスをとる必要はあるだろう。
アップルにとって飲めない部分ばかりだと、結局のところ、アップルは「法に従いつつ消費者を守る」という建て付けで、一部機能の提供を日本国内でも止める……という判断をしかねない。
それを持ち出すのは多少強引な話とも思えるが、「EUのように色々な機能が使えない状態になる」ことを、消費者が望んでいるわけではあるまい。
またここは面倒なところなのだが、OSのアップデートがあるとこの種の条件は細かく変わる。
例えば、秋に公開の「iOS 26」では、新しく「Wi-Fi Aware」という仕組みが設けられる。これはアップル製品と他社製品(周辺機器を含む)をWi-Fiをベースとした技術でつなぐ仕組みだ。こうした技術を使うと、他社が求めていたような「柔軟な接続」をiPhoneとの間で実現できる可能性も出てくる。
スマホ新法で求められる「公平な接続」も、そうした新技術の導入を前提に見直していける仕組みが必要になる。もちろん、「新しい実装に手間がかかる」という意見もあるだろう。その上での落とし所を見つけられるようなガイドラインが求められる。
Supercharge device connectivity with Wi-Fi Aware(WWDCセッションビデオ)
なお、この技術は一部で「AirDropの他社開放では」とも言われているが、ビデオ中でそうした話は出てこない。確かにそういう使い方もできそうだが、単純にAirDrop互換アプリが作れるものではない、というのが筆者の理解だ。
課金の安全性と自由のジレンマ
2つ目の課題は「課金のセキュリティ」だ。
課金の自由度拡大はスマホ新法の軸である。
一方でアップルは「詐欺やペアレンタルロックの効かない決済」の拡大を危惧している。
要は、アップルはそれらの課金が行なわれないように配慮しているが、単純に他の決済への回避手段を搭載すると、アップルの配慮を回避して詐欺や望まない課金が広がるのでは……としているわけだ。
これにも一理ある。アップルは「ここから先はアップルの課金システムではない」ことを明示的に表示するやり方を求めている。
一方で課金の自由度を求める企業は、「アップルの課金システムではない」という告知が出ることで消費者が逆に不安感を覚え、結局アップル以外の課金を使わないのではないか……という懸念を持っている。
現状でも、アップルやGoogleの課金システムを使わずに「ウェブ経由で決済する」ことは不可能ではない。サブスク系サービスへの加入では多いパターンだ。
だが先日、DMMが「DMM.TV」の新サービスを発表した際、面白いことを言っていた。
「これまではアプリ内からの加入と課金をしていなかったが、その仕組みを入れたら加入者が一気に増えた」というのだ。
これはゲームや電子書籍ではよく知られている現象。ウェブ経由にすると「難しい」「よくわからない」などの理由で顧客が課金に至る前に離脱してしまうため、価格が上がってもアプリ内課金を用意する……というパターンが多かった。「ここからはアップル(もしくはGoogle)の課金ではない」という警告の表示が消費者を戸惑わせるのでは、という懸念もよくわかる。
この現状は公平ではない、というところからスマホ新法はスタートしている。その点には筆者も同意する。
ただ同時に、アップルのいう「回避手段としての他社決済」という懸念も同時に理解できるのだ。
警告をやむを得ぬものと考えるのが妥当では、というのが筆者の意見だ。もしくはその文言や提示方法に歩み寄りがあってもいいだろう。
公平性は「将来」と「実効性」のバランスが肝要
これらの点を見た上で、「法が消費者の方を向いていない」「消費者が望んだものではない」という意見も目にする。
それはわかるが、それを非難するのは少しずれている、とも筆者は考える。
消費者に関わる法律は消費者のためであるべきで、その原則は間違いない。一方で、消費者が利便性の面で求めていないものでも、「今後の市場を考えた時には必要」なものは存在しうる。
公正競争は特にそうだ。競争が阻害されていても、良い機能があれば消費者としては満足である。だが中長期的に見れば、競争が行なわれないことは消費者にとってマイナスとなるため、公正競争を求める法規制が行なわれる。そのバランスは難しく、「今日の段階では消費者が求めたものではない」という流れにはなりやすくとも、必要ではあるのだ。
他方で、その競争の実効性を注視しておく必要もある。
サードパーティー製アプリストアは、競争上必要かもしれないが、現状の利用率からいうと、そこまで重視するものでもない。決済と自由度の透明性の方が大切だ。
あまり話題にならないが、検索エンジンについても第九条に「優先的に取り扱ってはならない」という規定がある。日本国内で代替検索エンジンを開発する動きはなく、国内事業者との競合という意味では実効性の薄い条文ではあるが、今後AIでの検索が広がることも考えると、検索サービスにおいて特定事業者の優越を禁じておくことは、公平性・透明性の観点で重要なことではある。
そう考えた時、アップルの主張のうち「意図を明確に」という要望は妥当なものではある。
EUでのデジタル市場法(DMA:Digital Market Act)は、明確にビッグテックを狙い撃ちにしたものであり、消費者の利便性以上に規制が重視された法律という見方もできる。
日本の場合、法案成立前にはDMA寄りな部分が見られたものの、結局は「無条件でのサイドローディングを導入しない」ことをはじめとした、セキュリティとプライバシーを重視した条項を追加し、DMAよりは消費者の方を向いた内容になったと感じる。
透明性と価値を担保する中で、アップルのいう「条件の明確化」という提案は重要なものだ。それを長期的な視点を維持した上でどうバランスをとるのか。
法の施行に向けたルール作りでは、そうした観点を重視して欲しい。