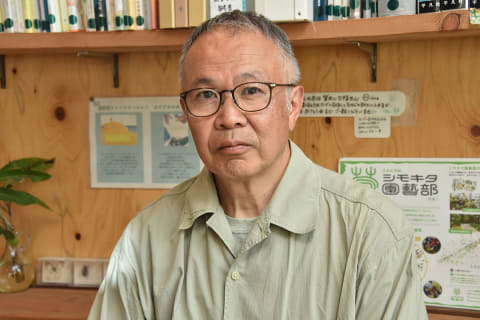トピック
下北沢の小田急線跡地で進む“本当の”緑化 シモキタ園藝部が創る緑の街
2025年6月4日 08:20
東京都世田谷区に所在する下北沢駅は小田急電鉄小田原線と京王電鉄井の頭線が交差する立地から、多くの来街者でにぎわう繁華街です。若者を中心に独自の文化を生んできた下北沢駅ですが、2013年に小田急の線路が地下化されて街の雰囲気が一変しました。
地下化の工事が進められていた当初から、世田谷区・小田急電鉄・周辺住民などが細長い線路跡地をどう活用するかを話し合ってきました。そして、約1.7kmの線路跡地は2022年に下北線路街として生まれ変わります。
同地は緑が溢れる空間になりましたが、これらの緑化で大きな役割を果たしているのがシモキタ園藝部です。シモキタ園藝部で代表理事を務める関橋知己さんとコンポスト事業担当の斉藤吉司さんの2人に、シモキタ園藝部の活動について話を聞きました。
芝生を張って緑化率を上げても本当の緑化とは言えない
――まず、関橋さんと斉藤さんがどのように下北沢の街と関わってきたのかをお伺いしたいと思います。
関橋:私はもともと東京・杉並区で生まれ育ちました。それから世田谷区に引っ越してきて、ずっと生活しています。最初から特に強くまちづくりの活動に関わっていたわけではありません。こうした活動を始める以前は、ごく普通の区民でした。
まちづくりの活動に関わるようになったのは、小田急電鉄の地下化に伴って下北沢駅周辺の跡地をどのように整備するのか? といったことについての世田谷区の計画イメージ図がポスティングされたことがきっかけです。
当初のイメージ図は緑がいっぱいで、地域住民が憩える場所になるということが想像できました。ところが、その後にイメージ図が急に変わります。最終案は2011年3月に出ましたが、それを見ると以前のイメージ図よりもアスファルトが大幅に増えている印象を受けました。
それを見て非常にショックを受けていたのですが、そのタイミングで世田谷区長が変わります。それで線路の跡地を緑豊かな公共空間として活用してくださいと提案しているNPOに加入して働きかけを始めました。
そのNPOはラウンドテーブルの場も提案していましたが、やがて北沢デザイン会議という行政・鉄道事業者・NPO・下北沢の企業や商店主・町会・住民といった誰もが話し合いに参加できる場が生まれました。
並行して、世田谷区が2016年に下北沢のまちづくりを考える北沢PR戦略会議を発足させます。現在も共同でシモキタ園藝部の代表理事をしている柏雅弘さんが中心となって、北沢PR戦略会議にはシモキタ緑部会という部会がつくられました。
こうした複雑な経緯をたどっていき、現在もやはり園藝部の代表理事をしているランドスケープデザイナーの三島由樹さんが、住民などが主体となって緑を管理する枠組みを小田急に提案し、シモキタ緑部会が発展する形でシモキタ園藝部になりました。
私は植物に興味・関心が強いというぐらいで、専門家ではありません。そのため、シモキタ園藝部の代表理事になるとは考えてもいませんでした。まさかこんなに広い面積の緑地の世話を主体的にするとは思ってもみなかったのです。当初はボランティア的な立場で手伝うくらいのイメージでした。それが流れと言いますか、巻き込まれちゃったという感じです(笑)。
斉藤:私は生まれが板橋区で、現在は目黒区に在住しています。世田谷との関わりは園藝部ができてからになりますが、それまでも自宅から世田谷まで日常的にランニングを楽しんでいました。私がよく走っていたのは北沢川緑道で、鎌倉通りとか面白い名前があると感じていました。
下北沢にはライブなどで足を運ぶ機会があるぐらいでした。仕事は建築関係なので、仕事外でもいろんなワークショップに参加していました。そうしたワークショップで生物多様性や環境について考えることが増えていたんです。
そんなとき、たまたまFacebookでシモキタ園藝部の話題が出てきたんです。それを見て「これは面白そうだ」と感じて3回目のワークショップから参加しました。ワークショップではプレゼン用の資料を用意してくださいとか、講演会を実施したりとか、どんどん活動に引き込まれていきました。
私も関橋さんと同じく緑の専門家ではなく、自宅の庭で花を植えたりしているぐらいです。ただ、自宅の庭に植えている花などに堆肥を与えるので、コンポスト(刈り取った草や落ち葉、剪定枝などから堆肥を作って土へと戻す)は自作しています。そうしたコンポストづくりが好きなので、シモキタ園藝部ではコンポストの担当をしています。
――最近、都内でも緑化の取り組みが始まっています。しかし、その多くは芝生を張って緑化した面積を増やして緑化率・緑被率を上げているという感じです。対して、下北沢の線路跡地は高木も多く、真の緑化といった雰囲気です。
関橋:高木を伐採して、その代替として芝生を張っても緑化率は変わりません。しかし、そういった緑化は本当の緑化ではなく、単なるグリーンウォッシュ(注:環境に配慮しているかのように見せかけること)だと受け止めています。なぜなら、生物多様性に寄与していないからです。
下北沢駅の線路跡地がきちんと緑化できているのは、なによりも多くの人が参加して緑を増やすことに協力的だからだと思っています。ただ、シモキタ園藝部は緑化だけをしているわけではありません。
例えば、循環ということを大切にして、落ち葉を環境改善に活かしたり、刈った草はコンポストで堆肥化しています。再開発エリアで住民が緑に親しめるようなイベントを開催したり、新しくする建物をなるべくコミュニティにも役立つようにする提案もしています。
そういう多くのアイデアを持っている人たちが集まって多彩な提案が出るので、小田急も面白がってくれるようになりました。小田急の担当者も提案を積極的に受け入れてくれています。
まちづくりに関わる人って、特に最近では面倒臭い人と思われてしまいますよね。ただ、下北沢は自然に住民がまちづくりに参加するような雰囲気になっていって、世田谷区も小田急もそれを面白がって取り入れてくれるようになりました。なので、反対運動と受け止められることはなく、お互いの立場も考えながら街の役に立てることを提案するような仕組みができるようになっています。
シモキタ園藝部の多くのメンバーはプロではなく緑が好きなだけ
――シモキタ園藝部では、緑化を中心にさまざまな事業を実施しています。例えば、「ちゃや」と呼ばれるカフェもそうです。ちゃやで注文するフレッシュハーブティーは、注文を受けてから「のはら」の圃場(ほじょう)エリアで育てたハーブを摘んできます。そのほかにも学校事業などを手掛けています。こうした緑を守るための経済システムが構築されていますが、これはみなさんで考えられたのでしょうか?
関橋:シモキタ園藝部の活動拠点となる「こや」「ちゃや」は、小田急から借りている建物なので、その家賃を払うためにも多角的に収益事業に取り組んでいます。これは立ち上げの時に何回もワークショップで話し合いをして、何のために稼がなければならないのかを明確化しました。
当初の話し合いで、シモキタ園藝學校はあくまでも、ここの緑を維持する担い手を育てることを目的にしていました。
なぜなら、シモキタ園藝部には緑のプロが少ししかいないからです。多くのメンバーは緑が好きなだけです。下北線路街の植栽管理は仕事として任されていますので、素人でもきちんと緑のお手入れができるように学ぶことが前提でした。
ところが、いざ始めてみると評判が広まっていったのか、最近ではランドスケープや造園会社といったプロの人まで受講するようになりました。園藝學校の講師を務めているのは立ち上げ当初からのメンバーの造園家ですが、真摯にカリキュラムを考え、受講生に向き合ってくれています。下北線路街をモデルにしながらも、コミュニティを巻き込み緑の資源循環を実現した植栽管理を実践的に学ぶコースに発展しています。
ちゃやで提供されているハーブティーは、のはらの圃場で育てた葉などを使っています。のはらは里山のように緑を暮らしに活かすことで緑が守られるという考えでデザインされています。そのデザインをした人もメンバーで、のはらの成長を見守りながら、ちゃやのマネージャーもしています。
これらシモキタ園藝部のメンバーは、地元住民ばかりではありません。外部から集まってきた人たちにも支えられています。
斉藤:シモキタ園藝部には凄いメンバーが集まっていますが、これは本当に不思議な縁としか言いようがありません。私は、こんな凄いメンバーが集まったのは、新型コロナウイルスが影響しているんじゃないかと考えています。
コロナの感染が拡大していた当時、みんなステイホームで気分が鬱屈していましたよね。外出もままならず、仲のいい友人と会うこともできない。そんな状況だったので、誰かとつながりたいとか何か新しいことを始めたいと考える人が多く、そうした気持ちがあったから一致団結できたのではないか、と。
関橋:小田急線の地下化した区間の上部である、下北線路街と呼ばれているのは東が東北沢駅付近で下北沢駅を挟んで西が世田谷代田駅付近までです。直線距離にすると約1.7km。細長い土地ですが、そこに多くの花や草木が植えられています。
このうち、緑のデザイン段階からシモキタ園藝部が関わったのは、のはら(シモキタのはら広場)と東北沢駅の周りの緑だけです。
ほかにも世田谷代田駅周辺や、下北沢駅から世田谷代田駅方面に向かった先に所在しているボーナストラックとか下北沢南西口の駅前広場も緑が溢れていますが、これは小田急が依頼した造園会社がそれぞれ植栽の方針を決めています。私たちの役割は完成した緑を引き継ぎ、維持・管理していくことです。
シモキタ園藝部は、今植えられている緑を元気に保つことを大切にしています。枯れてしまった木や花の代わりに何かを植えることはありますが、基本的には枯れてしまわないように緑を保っていくことが前提です。弱ってしまった木の樹勢回復も試みています。
見た目を重視して一年草の花を買ってきて植えて、それが枯れたらその花を抜いてまた新しい花を買ってきて植えるということを繰り返したくはありません。それでは、植物の命を無駄に消費財として扱っていることになります。できるだけ環境に合った樹木や多年草を植えるようにしたり、一年草を植えるにしても種でちゃんと繋いでいくことを意識しています。
公園と私有地のいいところ取りをした公共スペース
――のはらは、公園という位置づけになるんでしょうか? それとも農地になるのでしょう?
関橋:公園といえば公園になりますが、厳密には広場という扱いになっています。世田谷区には「身近な広場条例」という条例があり、一般的な都市公園のほかにも広場という扱いで公共空間や緑地を維持・管理する制度があります。条例で広場という名前がついていますが、都市公園法上の公園に相当します。のはら広場は世田谷区の管理するエリアと小田急電鉄の管理するエリアがシームレスにつながっていることが画期的です。
ただ、世田谷区のエリアは公園のルールが当てはまるので、勝手に花を植えたり摘んだりすることはできません。一方、小田急のエリアは植物を植えたり摘んだりといったことが可能です。摘むといっても、手入れの一環として伸びすぎた部分などを摘んでいるわけですが、その小田急の土地の一部で許可を得てハーブを栽培しています。
斉藤:のはらは公園と私有地のいいところ取りができている公共スペースと思っています。小田急の土地だからコンポストや納屋などをつくることができました。
園藝部の拠点である「こや」も、建物そのものは勝手に改築できませんが、内装は廃材を集めてきてメンバーの力でロフトや棚をしつらえました。購入した什器・備品も一部にありますが、それも配置や設置は自分たちでやっています。ただ、素人集団なので冷蔵庫の排水は簡易的にトレーで受ける形にしかできませんでした(笑)。そうした試行錯誤を繰り返しています。
――ちゃやで提供されているメニューも自分たちで考案したんでしょうか?
関橋:メンバーにハーブティーや野草を使ったおやつの考案など、草木の活用の先生をしている人がいます。その人に教わりながら、カフェ担当の人たちがハーブティーのメニューを考えました。ハーブティーだけではなく、クラフトコーラも提供しています。
また、ハーブティーの講習会や摘んだ雑草を加工して虫除けスプレー製作などのワークショップも開催しています。
そのほか、シモキタ園藝部では自作した下北沢産のハチミツ「シモキタハニー」も販売しています。以前から鎌倉などで養蜂をしていたメンバーが、自宅がある下北沢でもと提案してくれました。下北沢を本店にしている昭和信用金庫がシモキタハニーを知って、自社の屋上でも養蜂をしてほしいと場所を貸してくれました。それによって生産量を増やすことができ、シモキタ園藝部の取り組みが広がっています。
――シモキタ園藝部の原動力は多士済々のメンバーなんですね。
関橋:部員は積極的に集めているわけではないんですが、どんどん参加してくれる人が集まってきています。よく「どうやって部員を集めてるんですか?」と質問されることもあるんですが、特別なことはしていません。
斉藤さんのように区外から参加している人もいますが、特に下北沢周辺に住んでいる人が参加したいと声をかけてくることが多いんです。シモキタ園藝部は駅から近いところにありますので、駅からの行き・帰りで通りがかりますよね。それで目にして気になって、声をかけてくれるんだと思うんです。そこは、やはり下北沢という若者を中心に多くの人が集まる街の吸引力や、園藝部の「こや」が持っている場の力なのかなと思っています。
離れた地域にも広がるシモキタ園藝部のビジョン
――部員が増えてくると、そのうちシモキタ園藝部も下北沢支部、代田支部みたいに支部が生まれてくるようになるんでしょうか?
関橋:今の体制でも代田は範囲に含んでいます。ただ、下北沢から離れた地域でシモキタ園藝部の考え方に触発された活動が始まっていまして、〇〇園藝部と名乗ってもいいですか? という問い合わせをいただきます。
こちらは、特に名称を独占しているわけではないので「いいんじゃないですか」と返事をしています。同じビジョンを共有できるのだったら、そういった活動が広がる動きは歓迎しています。
斉藤:私は目黒区在住ですが、自宅の近くでシモキタ園藝部と同じような活動ができるなら、支部の設立を考えてみたいです。
目黒にも緑を育てたり、自然を守っていこうという団体はいくつかあります。それらの団体は、行政と連携して苗を植えたりする活動がメインです。緑を育てたり増やしたりすることはいいことですが、私はコンポストをやりたくてシモキタ園藝部の活動に参加しているので、そういった活動が目黒でもできるようになればいいな、と思っています。
ただ、世田谷側の人たちは、行政に対して「こういうのを植えたい」と積極的に行政へ提案しているんです。
一般的に住民たちが緑を守ろうとする活動は、その区から配布された草木や花をそのまま植えるだけという行政ありきの面がどうしてもあります。
そうした行政主体の活動を否定するわけではありませんが、やはり住民が主体になる活動の方が、自分たちの意識が反映されやすく、「〇〇を植えたい」と自由にできることが多いと感じます。シモキタ園藝部は、そうした能動的な点がほかの団体とは異なると感じています。
――話を聞いていると、シモキタ園藝部の活動はどんどん広がっていきそうに感じます。
関橋:活動そのものは順調だと感じていますが、ちゃややワークショップは基本的に大きな利益にはなりません。それらの収益で事業を支えるというよりも、むしろ緑にもっと親しんでもらうためのきっかけづくり、緑を感じてもらうための入り口だと捉えています。
だから多くの人が行き交う下北沢駅の近くにあって、散歩道の途中にあることが重要な意味を持っています。今までは自然に興味を持っていなかった人が、ふと立ち寄ったことで自然や緑に触れ、それが素晴らしいことに気づくんです。
そして、緑が素晴らしいことに気づけば、より自然や緑を大切にするようになります。
――下北沢駅に近いことが活動にもプラスに作用しているのですね。
斉藤:下北沢はサブカルの街というイメージが強いと思いますが、そのほかにも若者が多いので、新しいことを面白がって積極的に協力してくれるような雰囲気があります。
例えば、サステイナブルとコミュニティを実現するための商品や食体験を提供する「みんな商店」というお店があります。みんな商店は、ゴミを出さないように棚貸しをしたり、フルーツを発酵させた商品を製造・販売しています。そうした取り組みをしていても、食品残渣が出てしまいます。その出た残渣を乾燥させて発酵させるコンポストに入れてもらったり、ミミズの大好きなバナナの皮はミミズコンポストに入れてもらっています。
また、下北沢には「シモキタカレッジ」という寮がありまして、この寮は学生や若い社会人が生活していますが、その食堂から出た野菜クズもミミズコンポストに入れてもらい、土に還します。
発酵させるコンポストには、「ベルヴィルコーヒー」という下北沢でも人気のコーヒー店がコーヒー粕を、「東果堂」という果物屋さんが果物の種や皮を乾燥させて持ってきてくれます。
そのほか、近所のタイ料理屋さんが買ったものの置き場所に困ったものを再利用したコンポストもあります。昨年、このコンポストをくれたタイ料理屋の人たちが見に来てくれました。有効活用されているのをみて、すごく喜んでいました。
コンポストのほかにも、ビオトープをつくる計画を進めています。まず、田んぼのような場所をつくりますが、それをプラスチックのトロ舟で増設し、川のような水が流れるせせらぎをつくり、太陽光パネルを設置します。そこにポンプを設置して水を循環させる仕組みです。
こうした下北沢の店からも協力をしてもらっているので、シモキタ園藝部の活動は単なる一団体の活動ではなく、下北沢という街全体の取り組みに広がっているようにも感じます。
初心者でも参加OK
――ここまで話を聞いてシモキタ園藝部に参加してみたいという人もいると思います。園芸の初心者が参加する場合、最初はどんなことから教えてもらうんでしょうか?
関橋:まずは、緑のお手入れを学ぶことになります。お手入れの機会はたくさんありまして、その都度「いつどこどこでこれをやります」ということをお知らせしています。そのお知らせを見て、興味があるものに来てもらえれば、一緒に作業をしますし、そんなに難しいことはしません。だから、初心者でも問題ありません。
具体的には、草取りの作業が一番多くなります。草取りといっても、むやみに草を取っているわけではありません。雑草の役割も考えながら、選択的に整えています。その作業は、初めての人でも教えるので問題なくできます。ほかには水やりでしょうか。
畑ではないので、土を耕したりはしません。力を必要とすることもあまりありませんし、在来種の草木が中心ですから土を掘って肥料を与える作業も必要ありません。
斉藤:コンポストをきっかけにシモキタ園藝部に入りたいと希望する人は多いみたいです。コンポストの手入れ作業をしていると、通りがかりの人が声をかけてくれることがあります。
そういった声をかけてくれる方は、基本的にコンポストに興味があると思っています。ですので、自分でもやってみたいと思わせるように興味を高めてもらえるような説明をしています。
ただ、コンポストづくりは作業が大変なので、継続的に来てくれる人がもっと増えてくれたらという思いはあります。
関橋:現在、シモキタ園藝部の部員は約250名います。部員は多いのですが、約1.7kmのエリアを手入れするのですから、人が多すぎて場所が足りないということは起きません。
ただ、土日祝日に多くの人が手伝いに来てくれるのですが、下北沢駅の周辺は土日祝日になると、来街者が多く混雑します。
平日の方が落ち着いて作業ができる環境ですので、お手入れは平日の方がやりやすいんですが、みなさん仕事をしているので土日祝日しか参加できない人が多いんです。そのため、平日の人手確保が課題になっています。
――今後、シモキタ園藝部の活動を広げていく予定があったら教えてください。
関橋:活動内容としては生物多様性を高める植栽管理という意識が高まっていて、生き物の調査などを始めています。活動範囲としては下北線路街1.7kmの植栽の世話をしていますから、物理的な範囲的にも人員的にも、すぐに活動を広げていくことは難しいと考えています。
しかし、シモキタ園藝部の学校から毎年20人以上の卒業生を送り出しています。そういう人たちが希望すれば、活動を拡大することがあるかもしれません。
というのも、シモキタ園藝部の活動が少しずつ認知されるようになり、地域住民から「自宅の庭を管理してほしい」という要望や相談が寄せられるようになりました。そういう庭の管理などを引き受けることによって、下北沢という街全体の緑が増えることにもつながるかもしれません。
下北沢の緑が増えること、緑と人の関りが増えること、そうすることで街も人も緑も豊かになっていくことがシモキタ園藝部のビジョンだと考えています。