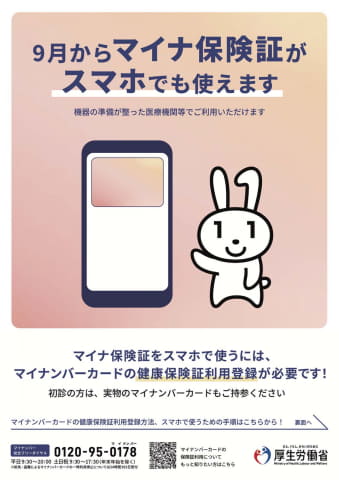ニュース
「マイナ保険証のスマホ利用」実証開始 9月から全国展開へ
2025年7月2日 20:08
6月24日にスタートしたiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載は、デジタル大臣の平将明氏によれば、サービス開始から1週間の6月30日時点で約66万5,000人の登録者に達しており、「非常に早いペースで登録をしていただき、ご利用いただいている」という。
一方で、iPhoneにマイナンバーカードが登録できるようになっても、まだまだ利用できる場面は少ないのが実情で、今後利用促進の鍵の1つとなるのが医療機関での「マイナ保険証」としての利用だ。
現状、医療機関等に設置されているオンライン資格確認のための「顔認証付きカードリーダー」は物理的なマイナンバーカードにしか対応しておらず、AndroidやiPhoneに登録されたマイナンバーカード機能(電子証明書)では利用できない。利用のためには外部に非接触のカードリーダー装置を別途取り付ける必要があり、これを踏まえた実証実験が始まっている。
厚生労働省によれば、7月に関東圏15の医療機関で「マイナ保険証がスマホで使える実証実験」を実施し、9月以降はそこで行なわれた問題の洗い出しと対策を踏まえたうえで全国の医療機関へと順次本格展開していくことになる。
7月2日には、同実証実験の参加医療機関の1つである国立病院機構東京医療センターに厚生労働大臣の福岡資麿氏とデジタル大臣の平将明氏が視察に訪れ、記者団を前に実証実験の意義などについて説明した。
実証実験の概要と9月以降の対応
両大臣は実際に手持ちのiPhoneに自身のマイナンバーカードを導入した状態で実証実験に参加しており、スマホ対応後の顔認証付きカードリーダーでの一連の操作を体験デモンストレーションを行ない、囲み取材での記者団への質問に答えている。
福岡厚労大臣
本日はマイナンバーカード機能を搭載した スマートフォンを今後、マイナ保険証として利用可能としていくための実証事業にご協力をいただいております国立病院機構東京医療センターを視察させていただきました。私自身も自分のスマートフォンを使って病院窓口の受付を体験させていただきました。
iPhoneとAndroid端末では使い方は少し異なりますが、いずれも簡単に受付できるということ、自分でもあっという間に終わったなという感じがしています。詳しい使い方につきましては、厚生労働省のホームページ等にリーフレットを掲載しておりますので、ご覧いただければと思っております。
実証事業につきましては、東京医療センターをはじめとする関東圏の15機関のご協力のもと、7月1日から7月18日、また8月4日から8月15日の2回に分けて実施をいたします。スマートフォンで受付をした場合に、円滑にかつ問題なくオンライン資格確認が行なわれるかについて、医療機関、薬局側、患者側の両側面から確認をしたいと考えています。その後、9月頃から環境が整った医療機関、薬局から順次運用を開始してまいりたいと考えております。具体的な時期につきましては、決まり次第発表いたします。
スマートフォンをマイナ保険証として使うには、マイナ保険証の利用登録をした上で、ご自身のスマートフォンで搭載手続きをしていただく必要がございます。国民の皆さまにおかれては、ぜひ手続きをしていただきたいなと思っております。 あわせて、医療機関や薬局側の準備としましては、スマートフォンの読み取りに対応したカードリーダーをご購入いただき、窓口に設置していただく必要があります。今般、購入費用の一部を補助することといたしました。8月中に補助を開始する予定ですので、医療機関、薬局の皆さまにおかれては、ぜひこの補助事業を活用していただければと考えております
平デジタル大臣も次のように述べている。
平デジタル大臣
マイナンバーカードの利活用の中でもマイナ保険証は非常に重要なユースケースであります。Android端末も含めカードがスマートフォンに搭載されることにより、より簡単なUI/UXで保険医療を受けられるようになることは国民の皆さまの利便性を大きく向上させるものと期待をしています。
私自身も最近財布自体を持っていないので、マイナンバーカードを使うとなると、それだけを(別に)持ってくる話になるので、これがスマホ1つで終わるとなれば、決済もほぼキャッシュレスですから、病院もスマホだけ持っていけばいいということになります。ただ、いま厚労大臣のお話にもあるとおり、医療機関への展開は9月から順次ということになりますので、スマホを持っていれば安心という話ではなく、確認のためにマイナンバーカードをお持ちいただき、行きつけの病院がスマホ対応だと確認できれば、以降はスマホだけで対応できることになり、利便性が向上します。
特にAppleの方は券面情報も搭載されますので、成人確認や住所の確認もできるようになり、民間のビジネスシーンでも利用の拡大が期待されるところです。デジタル庁としても、社会全体がDX、マイナンバーカードを活用したDX推進をしっかりと進めていきたいと考えています
記者団との質疑応答では、福岡氏の発言でも触れられた非接触カードリーダー装置を導入する医療機関への購入補助や、全国展開の目処などの質問が行なわれた。厚生労働省としては具体的な展開目標を定めていないものの、9月の全国展開までに15の医療機関で2回にわたって行なう実証実験を踏まえたうえで、さまざまな試行を経て本番に反映していきたいと回答している。
非接触カードリーダー装置の購入補助については、できるだけ多くの医療機関に導入してもらえるよう申請手続きを簡素化し、ECサイトを活用したクーポンによる補助なども検討しているという。厚労省の担当者に確認したところ、8月以降準備が出来次第、提供方法などのアナウンスを行なっていくという。
医療機関では、顔認証付きカードリーダー装置は院内の受付PCにUSB接続されており、今回のスマートフォン対応もさらにPCのUSB端子に別途“汎用のカードリーダー“を追加するだけの構造だ。購入補助の対象となるのは、(非接触)カードリーダーにUSBケーブル、(必要であれば)USBハブの3点。
顔認証付きカードリーダーについては、以前に購入補助の形で病院には3台、診療所が1台、薬局に1台の割り当てが行なわれたが、同様にカードリーダーについてもそれぞれ3・1・1の台数が各機関に購入補助対象として割り当てられる。予算感としては、カードリーダー自体が汎用のもので代用できるため、せいぜい数千円程度。補助全体の予算としても、仮に1医療機関あたり1万円と想定して、最大20万医療機関に対して20億に達しないレベルだという。
「スマホのマイナ保険証」利用手順
医療機関を受診する方々が実際にスマホでのマイナ保険証を体験するのは9月以降となるが、どのように受付方法が変化するのか、操作完了までのチャートをまとめたリーフレットを厚労省は配布している。
事前準備としては、スマートフォンに登録するマイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が開始されていること、そしてマイナンバーカードをAndroidまたはiPhoneのデバイス上に導入済みであることの2点が必要だ。
従来までであれば、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを(ケースを外した状態)で差し込むことで自動的に受付が開始されていたが、スマホからマイナ保険証を利用する場合は画面に表示される「スマートフォンを利用ボタン」を押して開始する。
次にiPhoneとAndroidのいずれのデバイスを資格確認に使うのかを選択。ここで両デバイスの操作方法が分かれるが、厚労省の配布するリーフレットでは上段がiPhone、下段がAndroidとなっている。iPhoneの場合、Face IDまたはTouch IDを使ってWallet内のマイナンバーカードのロックを解除した状態にし、先ほどの平デジタル大臣の写真にあるようにリーダーにそのまま"タッチ"すればいい。
一方のAndroidでは、画面にキーパッドが出現して「利用者証明用電子証明書」の"4桁の数字"を入力後、カードリーダーにスマートフォンを置くことでオンライン資格確認が行なわれる。
実際、現時点ではiPhoneの方がスムーズに認証が行なえている。
iPhoneにマイナンバーカード機能を登録したユーザーは6月30日時点で約66万5,000人。Androidでは2種類の電子証明書を選んで登録できるため数字が別々となるが、署名用電子証明書の登録者が25年5月時点で29万8,448、利用者証明用電子証明書は30万6,269となっている。開始から2年が経過したAndroidが約30万に対し、開始1週間で66万以上に達したiPhoneで勢いが異なるが、iPhoneユーザーはぜひ9月以降の展開で実際に利用してみてほしい。
医療機関に設置されている顔認証付きカードリーダー装置は定期的にソフトウェアアップデートがかかっているため、9月以降に実際にスマホでのマイナ保険証が利用可能になるタイミングでは、ソフトウェアで内部の処理を「スマホ対応」に切り替えるだけで利用できるようになると厚労省では説明している。前述の通りカードリーダー装置そのものは"汎用品"なので、購入してPCのUSBポートに挿し、ソフトウェアの設定を切り替えるだけですぐに利用可能になるというわけだ。
また、医療機関向けの顔認証付きカードリーダーは5つのメーカーが製品を出しているが、このうちキヤノンマーケティングのデバイスについてのみ、外付けのカードリーダー装置不要で本体のソフトウェアアップデートのみでスマホでのマイナ保険証利用が可能になる。
キヤノンの製品では子供などの背の低い人や車椅子での利用を想定して顔認証ができるよう、本体を取り外して利用できるようになっているほか、NFCのリーダー部分が孤立して存在しており、大型のスマホをリーダー部に差し込んでも読み取りが可能なためだ。厚労省によればキヤノンのリーダーを導入する医療機関の割合は15%程度とのことで、導入医療機関では受付のレイアウトを変更することなく、スマホでのマイナ保険証を利用できることになる。