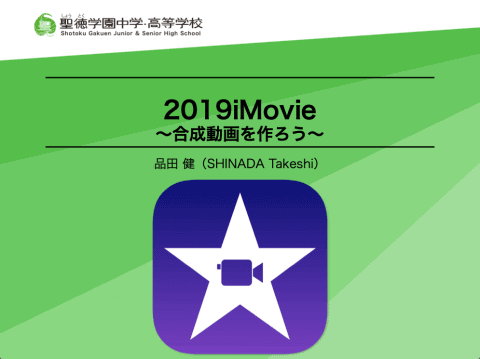こどもとIT
【連載】The Teachers' Voice~学びのアップデートをめざす先生からのメッセージ 第21回
効率化は教育ICTの目的ではない。手探りのSTEAM教育と失敗経験から気づいた大事なこと
〜聖徳学園中学・高等学校 品田健教諭がめざす学びのアップデート③
2021年2月17日 06:45
生徒の活動時間を増やしたい一心で、効率化が裏目に
私が受け持つSTEAMの授業は、生徒が取り組むプロジェクトの大半を1から考えて作っています。もちろん、失敗もたくさんあり、最初のクラスでやってみて上手くいかず、修正して何とか形になることもあります。
第1回目の記事でご紹介した「火星ゲーム」については、初年度はまるで上手くいかず、悩みました。自分では「これは面白い!生徒も絶対ノってくるはずだ」と予想していましたが、実際のところ、生徒たちは楽しめておらず、出てくる考えや意見も今ひとつ深まっていませんでした。
ところが、ある生徒と話をしたとき、「映画の話がよくわからず、自分もその世界に入っていけない」と言われ、初めて気づきました。映画の中では、火星に残された生存者を救出するかどうかは大問題なのかもしれないけど、その生徒は自分事として受け止められないというのです。
無理もありません。授業では、少し長めの予告編を見せて、あとは内容を簡単にまとめたスライドを使って説明し、「皆さんならどうしますか?」と投げかけていたのですから。これでは、生徒はストーリーもよくわからないし、興味を持てるか難しいですよね。
私は当時、少しでも生徒の活動時間を増やしたくて、どうすれば説明に費やす時間を減らせるか、効率化のことばかり考えていました。本来であれば、ストーリーを理解してもらい、「自分だったらどうするだろう」と考えてこそ意味のある取り組みですが、その部分を一気に端折ってしまい、生徒を置き去りにしてしまっていたのです。
そこで翌年度からは、オープニングの30分程を観るようにしました。50分の授業ですから、効率化だけ考えたらもったいない時間の使い方です。
ところが生徒のプロジェクトへの取り組み方は、全くと言っていいほど変わりました。30分という時間で映画の出来事が自分事化され、火星からの救出は技術的に実現可能かどうかを、日本語のウェブサイトだけでなく英語のウェブサイトで調べたり、理科の教員に質問する生徒もいました。
また「巨額の費用をかけて、火星にいる一人を助けるのか、その費用で地球にいる大勢の困っている人を助けるのか」という倫理的な視点でも考えたり、「そもそも生存者の情報を隠蔽すればいいのではないか」という意見に対しても、ただのウケ狙いではなく、そうした場合にどんな問題が起こるかまで考えられるようにもなりました。
ICTを活用して授業の効率化を進めることは悪いことではありません。ただし、本当に大事なところに時間をかけられるように計画された効率化であることが大切です。
かつての私のように、単純に時間の節約を考えて効率化してしまったら、結果はかえって悪い方向に流れてしまいます。ICT活用のメリットとして、授業の効率化が挙げられますが、何のための効率化なのか、効率化したことでマイナスの影響はないのかをよく考えることが大切です。
教師が作った説明動画、生徒が一番よく見ているものは?
私が現在進めているのは、アプリケーションやサービスの使い方など、技術的な説明に費やす時間を効率化することです。授業内では簡単に一度だけ説明し、あとは生徒たちが動画やデジタルテキストを見て理解できるようにしています。
これは、コロナ禍のオンライン授業で気づいたのですが、生徒の理解度が見えづらいオンライン授業では、「わかっているのかな?」という不安から何度も説明を繰り返しがちです。そこで教師の説明時間を減らすために、説明内容をデジタルテキストとして読めるようにしたり、説明を動画にしてYouTubeで限定公開してみたのです。その結果、YouTubeの再生回数と、生徒が提出した作品を見て、「自分は今まで、なんてくどい説明を繰り返してきたのだろうか」という結論に至りました。
一般的にYouTubeの投稿は、再生回数が多くて離脱率の低いものが、動画として高い評価を得ています。しかし、私は自分の動画については、再生回数が少なくて、離脱率が高いものが良いと考えています。なぜなら、生徒たちは授業内の説明で理解できていれば、そもそも動画を観る必要がないからです。また、最初から最後まで全部観ないと理解できない動画よりも、途中で理解し離脱できた方がいいと考えています。
実際に、あるプロジェクトでYouTubeに掲載した動画の再生率をみると、アプリケーションの操作については71%、取り組む課題の説明については39%、課題の提出方法については84%でした。アプリケーションの操作については、一回の説明で理解できない生徒もいますし、考査前に復習として観る生徒もいたようで、生徒の7割程度はもう一度説明動画を観ています。
しかし、生徒たちが取り組む課題について説明した動画は4割も見返していません。この程度であれば、わざわざ繰り返さなくても十分だったのでしょう。一方で成績に関係するプロジェクトの説明動画は何と8割以上の生徒が視聴しています。初めて使うサービスだったことも一因かもしれませんが、ここは授業でしっかり説明しても良かったと思います。
動画があればデジタルテキストは不要と思われるかもしれませんが、これも生徒の声で気づかされ、授業で使ったKeynoteのスライドをまとめてデジタルテキストにしています。全体の説明をもう一度聞きたいという生徒はYouTubeの動画を観ますが、わからない部分だけを知りたい生徒にとっては、動画は面倒で、デジタルテキストの方がピンポイントで調べられて良いのだそうです。
生徒たちにとって、理解するための手段が選べることは大事であり、ICTの導入の効果として語られる個別最適化された学びは、このような対応が必要だと思います。
「教科書を使って授業をしてください」と言われ続けても……
このような失敗を繰り返しながら、私は生徒が自分なりに問題や課題を見つけ出せるようなプロジェクトを考えてきました。そして課題解決のために、生徒が身につけた知識や技術を使ってチャレンジできたら、深い学びにつながるだろうと試行錯誤を続けてきました。
しかし、それって学校でやることなのか。授業で取り組むことなのか。大学に進学してから専門分野でやればいいのではないか。そう思われる方もいるでしょう。実際に、生徒や保護者にもこうした授業は当時受け入れ難いものだったようです。
私が聖徳学園に移って初年度の授業アンケートでは、「情報の授業をちゃんとやってほしい」「教科書を使って授業をしてください」「WordやExcelの操作を中心に」といった要望をもらいました。さらには、担任の先生経由で「保護者が先生の授業は何をしているのかわからないって仰ってました」と聞かされたこともあります。
私もかつては誰よりもそういった要望通りに「教えたい」教師だったので、そんな授業をしてほしい生徒や保護者の気持ち、とてもよくわかります。それでもSTEAM教育に取り組んでいく中で、生徒の学びが深まる瞬間を目にしたり、私たちが想像もしなかったような作品を生徒が創造した場面に出会ったりすることで、生徒も私も成長を実感し、互いに自信を深めていきました。
もちろん、今でも稀に「もっと教科書を使ってほしい」という意見をいただくことがあります。しかし、実践を重ねていくことで、そういった不安や心配を払拭できる成果も積み重なり、生徒にも保護者にも理解をいただけるようになりました。
第4回は、「正解のない問い」について掘り下げていきます。
The Teachers' Voice 目次
- 生徒たちが使う端末に制限はかけさせない。こだわり続けた自由度の高いiPad導入〜近畿大学附属高等学校 乾武司教諭(全5回)
- 読み書き計算に困難のある子の学びを支える"オーダーメイド”の支援 〜つくば市立学園の森義務教育学校 山口禎恵教諭(全3回)
- へき地が抱えるICT環境の課題と、教員の世界を広げるSNS活用 〜青森県 つがる市立育成小学校 前多昌顕教諭(全2回)
- コロナ禍で見えた新しい学びのカタチ「Face to Face の教育から、学びのSide by Sideへ」 〜東京学芸大学附属小金井小学校 鈴木秀樹教諭(全5回)
- 英語を学ぶだけではない、ICTで生徒が自己発見できる学びとは? 〜工学院大学附属中学校・高等学校 中川千穂教諭(全3回)
- ICT活用が進まない本当の理由は、教師の中に潜む“使命感”にある 〜聖徳学園中学・高等学校 品田健教諭(全5回)
- 教育版マインクラフトの学習に初挑戦。授業に落とし込む前に考えたこと〜大森学園高等学校 杉村譲二教諭(全3回)