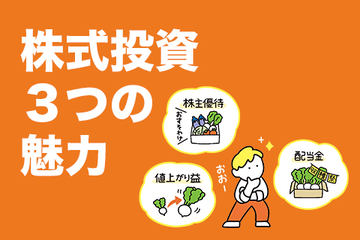from Impress
【いちからわかる!株入門6】企業の経営効率を判断する「ROE」
2024年5月23日 09:00
株式の銘柄探しにおける3つの指標について連載で紹介します。気になる企業へ投資するにあたり、その企業が効率的な経営ができているかは気になるポイントです。自己資金を投資しても、企業がそのお金をうまく使えなければ将来性は低いといえます。ここでは、企業の経営効率を判断する「ROE」指数について解説します。
この記事は4月16日発売のインプレス刊『いちからわかる!株入門 2024年新NISA対応版』(和島英樹 監修)の一部を編集・転載しています。掲載されている銘柄情報などは2024年3月時点のデータです(編集部)
株式資本を効率的に活用しているかの指標
「ROE(自己資本利益率)」は、企業の経営効率を測るための財務指標です。自分たちが投資したお金を企業が効率よく使えていれば、将来性のある企業だと判断できます。
ROEは「当期純利益」を「自己資本(純利益)」で割って算出します。この自己資本は、投資家から集めた資金で構成されています。つまり投資家目線では、自分たちが出資した資金を使って、企業が効率よく稼いでいるかどうかの指標となります。基本的にはROEが高いほど効率よく稼いでいる企業といえます。
なお、計算式に株価が含まれておらず、ROEでは株価の割安性は判断できません。企業の収益力や競争力の評価指標であり、ROEの高い銘柄は今後の株価上昇や配当増加が期待できるといえます。
また、純利益には借入金などの負債は含まれていません。ROEは高いものの、多額の負債を抱えている場合は、効率的な経営をしているとはいえないため注意が必要です。総合的な業績を見て判断しましょう。
ROEの目安は8~10%以上あるのが理想
ROEは8%以上を1つの目安として考えるといいでしょう。理想は10%以上、15%以上ある場合はかなり効率よく経営できているといえます。
ただし、PERの平均が業種によって異なったのと同じように、ROEも業種によって平均値が異なります。一般的に情報・通信業や卸売業、鉱業はROEが高い傾向にあり、電気・ガス業や飲食サービス業は低い傾向にあります。ROEも数値だけを見るのではなく、同じ業種や似たような事業内容の企業と比べて判断することが大切です。
また、ROEと似た指標でROA(総資産利益率)と呼ばれるものがあります。これは借入などの負債も含めた全資産に対してどのくらい利益をあげたかを示す指標です。ROEが高くてもROAが低い場合は、資産の負債割合が多くなっている可能性があります。銘柄選びの際は1つの指標だけを見るのではなく、割安度や会社の収益性、経営効率など多角的に判断しましょう。
株式投資の魅力から成長株探しまで全6回で連載
第6回:企業の経営効率を判断する「ROE」
・価格:1,100円
・発売日:2024年4月16日
・ページ数:112ページ
・サイズ:A4変型判
・監修:和島英樹
内容
1章 株の基礎知識
2章 口座座開設と売買方法
3章 銘柄の絞り方
4章 売買のタイミング
5章 銘柄ランキング 株主優待編/高配当編
・監修プロフィール
和島 英樹 (わじま ひでき)
経済ジャーナリスト
現みずほ証券、株式新聞社(現ウエルスアドバイザー)記者を経て、2000年にラジオNIKKEIに入社。東証・記者クラブキャップ、解説委員などを歴任。2020年6月に独立。企業トップへの取材は1,000社以上。近著に「1万円からはじめる勝ち組銘柄投資」(かんき出版)。レギュラー出演番組にラジオNIKKEI「マーケット・プレス」、東京MXテレビ「東京マーケットワイド」、日経CNBC「朝エクスプレス」など。週刊エコノミストなど雑誌への寄稿も多数。日本テクニカルアナリスト協会評議委員。